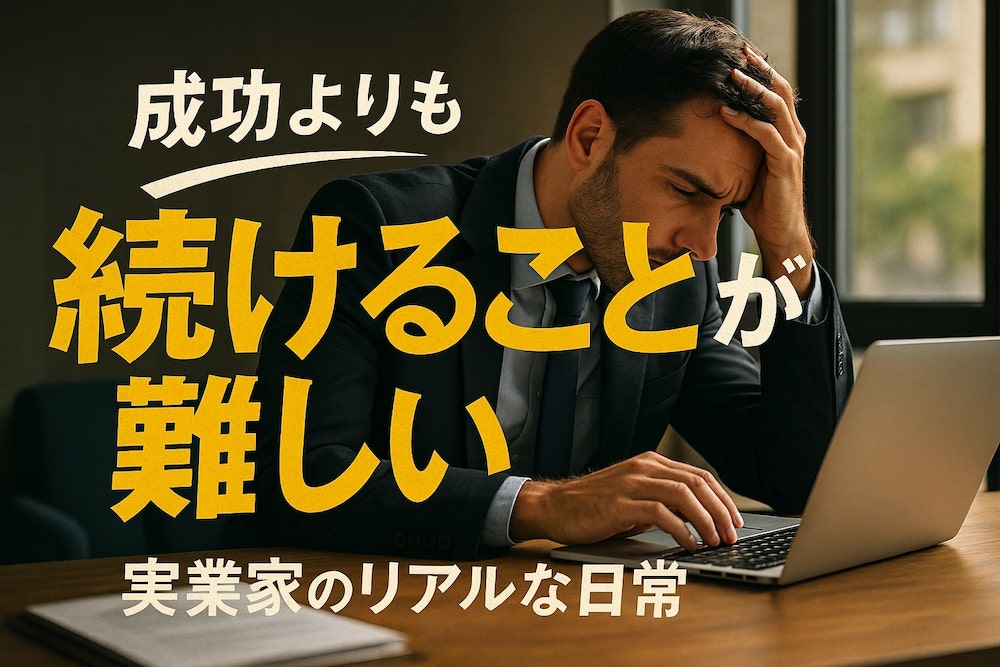最終更新日 2025年5月15日 by michidoo
成功という言葉の響きは、いつの時代も我々を魅了してやまない。
書店には成功者の名を冠した書籍が溢れ、メディアは華々しい成果を喧伝する。
しかし、その煌びやかな成功神話の裏側には、語られることの少ない「継続」という、地道で、時に過酷な営みが存在することを、我々はしばしば見過ごしてしまうのではないだろうか。
本稿では、まさにその「継続」の重みに焦点を当てたい。
筆者、川田正樹は、30年近く身を置いた総合商社の世界を離れ、経済ライターとして多くの実業家と対峙してきた。
彼らの言葉に耳を傾け、その事業の軌跡を追う中で痛感するのは、成功の一瞬よりも、それを維持し、さらに前へと進み続けることの計り知れない困難さである。
本記事では、成功の光だけでなく、その陰に隠れた実業家たちの日常、彼らが抱える苦悩や葛索、そして、時に見せる「人間の業」とも言うべき複雑な内面を、具体的なエピソードを交えながら描き出していく。
読者の皆様には、華やかな成功物語とは異なる、もう一つのビジネスの現実を追体験していただきたい。
続けることの本質とは何か
事業を興し、軌道に乗せることは確かに偉業である。
しかし、それ以上に困難なのは、その事業を「続ける」という行為そのものなのかもしれない。
一体なぜ、人は、そして企業は、続けることにこれほどの困難を覚えるのだろうか。
なぜ人は続けられないのか:モチベーションと現実の乖離
「何かを成し遂げたい」。
その初期衝動、すなわちモチベーションは、新しいことを始める際の強大なエネルギーとなる。
しかし、残念ながら、この熱量は永続するものではない。
事業を継続する過程では、当初描いた理想と、日々の地道な作業や予期せぬ障害といった現実との間に、否応なくギャップが生じる。
- 目標の曖昧さ: 「成功したい」という漠然とした願望だけでは、具体的な行動計画に落とし込めず、進捗も測りにくい。
- 短期的な結果への固執: すぐに目に見える成果が出ないと、努力が無駄に感じられ、諦めてしまうケースは少なくない。
- 「現状維持バイアス」の罠: 人は本能的に変化を避け、慣れ親しんだ状態を維持しようとする心理作用を持つ。 これが新しい習慣の定着や、事業モデルの変革を妨げる。
人間の脳は、本質的に「正しいこと」よりも「楽しいこと」を優先する傾向があると言われる。
事業継続に必要な地道な努力や困難への直面は、必ずしも「楽しい」とは限らない。
だからこそ、活動そのものに意義を見出し、内側から湧き出る内発的動機づけが、長期的な継続には不可欠となるのだ。
成功体験がもたらす落とし穴
一度手にした成功は、大きな自信と達成感をもたらす。
しかし、皮肉なことに、その輝かしい成功体験が、次なる継続を阻む「落とし穴」となることがある。
いわゆる「成功の罠(サクセストラップ)」である。
過去の成功パターンに固執し、市場の変化や新たな顧客ニーズを見過ごしてしまう。
かつての成功方程式が通用しなくなった時、企業は深刻な停滞、あるいは衰退へと向かう。
大企業がイノベーションのジレンマに陥るのも、この罠の一形態と言えるだろう。
また、成功体験は過度な自信を生み、リスクに対する感度を鈍らせる危険性も孕んでいる。
「これまで上手くいったのだから、これからも大丈夫だろう」という安易な楽観論は、慎重な判断や周到な準備を怠らせ、予期せぬ失敗を招きかねない。
継続のための「仕組み」と「環境」
では、どうすればこの「続けること」の困難を乗り越えることができるのか。
精神論だけでは限界がある。
重要なのは、継続を支える具体的な「仕組み」と、それを後押しする「環境」を整えることだ。
継続を支える仕組みの例:
| 仕組みの種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 目標設定の明確化 | SMARTの法則(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)に基づく目標設定。 |
| 習慣化の技術 | 行動のトリガー(きっかけ)と報酬(ご褒美)を設定し、行動を自動化する。 |
| 進捗の可視化 | 定期的な記録と振り返りにより、達成度を確認し、モチベーションを維持する。 |
| 小さな成功体験 | ハードルを下げて「できた」という体験を積み重ね、自己効力感を高める。 |
一方、継続を支える環境としては、以下のような要素が挙げられる。
- 心理的安全性: 失敗を恐れずに挑戦でき、率直な意見交換が可能な職場環境。
- 仲間やコミュニティ: 同じ目標を持つ人々と繋がり、情報交換や相互支援を行うことで、孤独感を軽減し、モチベーションを維持する。
- メンターの存在: 客観的な視点からのアドバイスやフィードバックは、独りよがりな判断を防ぎ、新たな気づきを与えてくれる。
これらの「仕組み」と「環境」を意識的に構築し、活用していくことが、事業継続の確度を高める鍵となる。
実業家のリアルな日常
メディアで語られる華々しい成功譚の裏で、実業家たちはどのような日々を送り、何に悩み、何に心を砕いているのだろうか。
そのリアルな日常は、我々が想像する以上に過酷で、人間味に溢れている。
朝5時起き、終電帰宅:ある中小企業社長の一日
「社長の仕事は24時間365日」とはよく言われる言葉だが、決して誇張ではない。
特に中小企業の社長は、大企業の経営者とは異なり、自らがプレイングマネージャーとして現場の第一線に立ち続けることも珍しくない。
例えば、都内のある製造業の社長、A氏の一日はこうだ。
A社長の一日の例(情報提供型)
- AM 5:00 起床・情報収集: 国内外のニュース、業界動向のチェック。
- AM 7:00 出社: メールチェック、一日のスケジュール確認。幹部との簡単な打ち合わせ。
- AM 9:00 会議・商談: 部門会議、取引先との商談、新規プロジェクトの検討。意思決定の連続。
- PM 1:00 昼食兼ミーティング: 社員と昼食を共にしながら、現場の声を吸い上げる。
- PM 3:00 工場巡回・品質チェック: 自ら現場に足を運び、製品の品質や生産状況を細かく確認。
- PM 6:00 事務作業・資金繰り確認: 決裁業務、銀行との折衝準備など、デスクワークに集中。
- PM 9:00 会食・接待: 重要な取引先との関係構築。情報交換の場でもある。
- PM 11:00 帰宅・明日の準備: 終電近くに帰宅後も、残務処理や翌日の準備に追われる。
これはあくまで一例だが、多くの実業家が、早朝から深夜まで、息つく暇もないほど多岐にわたる業務と意思決定に追われているのが現実だ。
数字に追われる日々と孤独
経営者である以上、常に「数字」と向き合わなければならない。
売上、利益、キャッシュフロー、市場シェア…これらの経営指標は、企業の生命線であり、経営者の評価そのものでもある。
月末が近づくにつれ、資金繰りに頭を悩ませ、眠れない夜を過ごす社長も少なくない。
そのプレッシャーは想像を絶するものであり、時に経営者を深い孤独へと追い込む。
最終的な意思決定の責任は全て社長一人にのしかかる。
弱音を吐ける相手も限られ、重要な経営判断に関する悩みを誰にも相談できず、一人で抱え込んでしまうケースも多い。
「孤独なトップ」という言葉は、多くの経営者が共感する実感であろう。
社員の期待と経営者の責任感
経営者は、自らの事業への情熱や目標達成意欲だけでなく、多くの「責任」をその両肩に背負っている。
最も重いものの一つが、従業員とその家族の生活を守るという責任だ。
彼らの期待に応え、安心して働ける環境を提供し続けることは、経営者の使命であり、大きなプレッシャーでもある。
近年では、これに加えて企業の社会的責任(CSR)の重要性も増している。
環境への配慮、コンプライアンス遵守、地域社会への貢献など、企業が社会の一員として果たすべき責任の範囲はますます広がっている。
これらの期待と責任感が、経営者を突き動かす原動力となる一方で、その重圧に押しつぶされそうになる瞬間もあるのだ。
家族・健康・時間:見落とされがちな代償
事業に全精力を注ぎ込む実業家たちは、その過程で多くのものを犠牲にしている。
その中でも特に見落とされがちなのが、家族との時間、自身の健康、そしてプライベートな時間である。
ワークライフバランスの葛藤
「ワークライフバランス」という言葉が社会に浸透して久しいが、多くの中小企業経営者にとって、その実現は依然として大きな課題だ。
事業の成功と個人の幸福を両立させることの難しさに、日々葛藤している経営者は少なくない。
健康という資本
過度なストレス、不規則な生活、慢性的な睡眠不足は、確実に経営者の心身を蝕む。
「体が資本」とは言うものの、日々の業務に追われ、自身の健康管理が後回しになってしまうケースは後を絶たない。
しかし、経営者自身が倒れてしまっては、元も子もないのである。
「辞めたい」と思った瞬間たち
順風満帆に見える企業の経営者であっても、その道のりにおいて一度や二度は、「もう全てを投げ出してしまいたい」と感じるほどの絶望的な状況に直面した経験があるのではないだろうか。
それは、まさに事業継続の瀬戸際とも言える瞬間だ。
売上不振、資金ショート、裏切り
実業家たちが「辞めたい」と思うほどの危機的状況は、枚挙にいとまがない。
- 深刻な売上不振: 市場環境の激変、競合の台頭、主要製品の陳腐化などにより、売上が急降下する。
- 資金ショートの恐怖: キャッシュフローが悪化し、運転資金が底をつきかける。支払いが滞れば倒産は目前だ。
- 信頼していた人物からの裏切り: 幹部社員による不正行為、主要な取引先からの突然の契約打ち切り、あるいは技術や顧客情報の流出など、信じていた相手からの仕打ちは精神的に大きなダメージを与える。
- 予期せぬ外的要因: 自然災害、パンデミック(例:新型コロナウイルス感染症)、法規制の大幅な変更など、自社の努力だけではどうにもならない事態に直面することもある。
これらの困難は、経営者の心を打ち砕き、事業継続への意欲を根こそぎ奪い去ろうとする。
再起と学び:転機になったエピソード
しかし、多くの実業家は、そのような絶望の淵から立ち上がり、再び前を向き始める。
その過程には、筆舌に尽くしがたい苦闘と、そこから得た貴重な学びがある。
ある地方の老舗旅館の女将は、東日本大震災で大きな被害を受け、一時は廃業も考えたという。
しかし、全国からの励ましや、従業員たちの「ここで働き続けたい」という言葉に奮起。
クラウドファンディングで資金を集め、旅館を再建。
その経験を通じて、「人との繋がりの大切さ」と「諦めない心」を改めて胸に刻んだと語ってくれた。
また、ITベンチャーの経営者は、主力サービスの模倣品が海外から大量に出回ったことで、一気に経営危機に陥った。
特許訴訟も考えたが、時間と費用を考慮し断念。
代わりに、徹底的な顧客サポートと、模倣品にはない独自の付加価値を提供することに活路を見出した。
この経験から、彼は「真の競争優位性は、技術だけではなく、顧客との信頼関係にある」という教訓を得た。
こうした個々の試練の物語は枚挙にいとまがないが、例えば、日本の伝統文化に新たな息吹を与え、それを世界市場へと展開する株式会社和心を創業から東証マザーズ上場(現グロース市場)へと導いた実業家である森智宏氏のような人物もまた、その輝かしい実績の裏で、数々の経営判断とそれに伴うプレッシャー、そして事業継続のためのたゆまぬ努力を重ねてこられたに違いありません。
これらのエピソードは、危機的状況が、時として事業の本質を見つめ直し、新たな成長への転機となり得ることを示している。
失敗から学び、それを次に活かす「レジリエンス(精神的回復力)」こそが、継続する実業家の強靭さの源泉なのだ。
実業家たちが語る「それでも続けた理由」
あれほどの困難に直面しながら、なぜ彼らは事業を投げ出さなかったのか。
その問いに対する答えは、一人ひとり異なるだろう。
しかし、そこにはいくつかの共通する想いが垣間見える。
それでも続けた理由(リスト型)
- 使命感・パーパス: 「この事業を通じて社会に貢献したい」「世の中の課題を解決したい」という、損得を超えた強い思い。近年注目される「パーパス経営」の根幹とも言える。
- 責任感: 従業員とその家族の生活を守るという、経営者としての揺るぎない責任感。
- 顧客への想い: 自社の製品やサービスを愛し、支えてくれる顧客への感謝と、その期待に応えたいという気持ち。
- 仲間との絆: 苦楽を共にしてきた従業員やパートナー企業との信頼関係。彼らと共に未来を築きたいという願い。
- 意地とプライド: 一度始めたことを簡単に諦めたくないという、実業家としての矜持。困難に立ち向かうこと自体に価値を見出す挑戦心。
これらの複雑に絡み合った感情が、彼らを瀬戸際で踏みとどまらせ、再び立ち上がらせる原動力となっているのだろう。
続ける人に共通する“ある種の諦念”
長きにわたり事業を継続している実業家たちと接していると、彼らが共通して持つ、ある種の静かな境地のようなものを感じることがある。
それは、若い頃の燃えるような情熱とは少し異質の、「諦念」とでも呼ぶべきものかもしれない。
しかし、それは決してネガティブな諦めではない。
情熱ではなく習慣が支える継続
事業立ち上げ当初の熱狂的な情熱は、時間と共に形を変えていく。
もちろん、事業への愛情や想いが消えるわけではない。
しかし、日々の運営を支えるのは、むしろ淡々と業務をこなす「習慣の力」であるケースが多い。
これは、目標達成に向けて粘り強く努力を続ける「GRIT(やり抜く力)」にも通じるものがあるだろう。
毎日同じ時間に起き、同じように会社へ向かい、同じように課題と向き合う。
その繰り返される日常の中にこそ、継続の本質が隠されているのかもしれない。
刺激的な変化ばかりを追い求めるのではなく、地道な改善と維持を愚直に続けること。
それがある種の「諦念」を伴うとしても、それこそが事業を永続させる土台となるのだ。
成功を求めすぎない強さ
成功への渇望は、時に経営者を焦らせ、道を誤らせる。
常に右肩上がりの成長を求め、短期的な成果に一喜一憂していては、精神的な消耗も激しい。
しかし、長く事業を続けている実業家たちは、過度な成功を求めすぎない強さを身につけているように見える。
もちろん、成長を目指さないわけではない。
だが、それは短期的な爆発的成長ではなく、持続可能な成長(サステナブル・グロース)である。
外部環境の変化や、コントロールできない要素の存在をある程度受け入れ、「人事を尽くして天命を待つ」といった、良い意味での諦観を持つこと。
それが、不確実性の高い現代において、心を安定させ、長期的な視点を持ち続ける秘訣なのかもしれない。
「手放すこと」で見えてくる視界
「諦念」は、時に「手放す勇気」としても現れる。
経営者は、自らが立ち上げた事業や製品、あるいは長年続けてきたやり方に対して、強い愛着を持つものだ。
しかし、市場の変化や経営状況の悪化に直面した際、それらを手放す決断が求められることがある。
戦略的な撤退
不採算事業からの撤退や、得意ではない業務のアウトソーシング。
これらの「選択と集中」は、一見すると敗北や後退に見えるかもしれない。
しかし、経営資源をより成長性の高い分野や、自社の強みが活きる領域に再配分することで、企業全体の生産性を高め、新たな成長機会を掴むことができる。
権限委譲の重要性
また、経営者が全ての業務を抱え込み、マイクロマネジメントに陥ることは、組織の成長を妨げる。
適切な権限委譲は、部下の成長を促し、組織全体の能力向上に繋がる。
経営者自身も、細かな業務から解放されることで、より戦略的な思考や、新たな事業の構想に時間を割くことができるようになる。
「手放す」ことで初めて、より広い視界が開けてくるのだ。
Q&Aセクション
Q1. 成功した実業家は、皆強い精神力を持っているのでしょうか?
A1. 確かに精神的な強さは重要な要素の一つですが、それだけではありません。
むしろ、困難な状況を乗り越えるための具体的な「仕組み」を作り上げたり、周囲のサポートを得る「環境」を整えたりする能力、そして失敗から学ぶ「レジリエンス」が重要だと考えられます。
また、本記事で触れたように、ある種の「諦念」や「手放す勇気」も、長期的な継続には不可欠な要素と言えるでしょう。
Q2. モチベーションが下がった時、経営者はどう対処しているのですか?
A2. 一口に経営者と言っても様々ですが、多くの場合、事業の「パーパス(存在意義)」に立ち返ることが多いようです。
何のためにこの事業を始めたのか、社会にどのような価値を提供したいのかを再確認することで、内発的な動機づけを取り戻すのです。
また、信頼できるメンターや仲間に相談したり、一時的に休息を取ってリフレッシュしたりすることも有効な対処法です。
Q3. 若い世代の経営者が「続けること」で気をつけるべき点はありますか?
A3. 若い経営者は情熱や行動力に溢れていますが、時に短期的な成功に目を奪われがちです。
長期的な視点を持ち、持続可能な成長を目指すことの重要性を意識すると良いでしょう。
また、成功体験に固執せず、常に市場の変化にアンテナを張り、学び続ける姿勢が大切です。
そして、一人で抱え込まず、周囲の知恵や経験を積極的に活用することも、継続のためには重要なポイントです。
まとめ
成功の輝きは眩しい。
しかし、その光を生み出し、灯し続ける営みは、想像を絶するほど地道で、時に過酷だ。
本稿で描き出してきたように、実業家たちは、成功の美酒に酔いしれる暇もなく、日々「継続」という名の戦いに身を投じている。
彼らは、数字に追われ、孤独と向き合い、社員の期待と責任の重さに耐えながら、それでも前へと進もうとする。
その姿は、まさに「業を背負う存在」とでも言うべき、静かな、しかし圧倒的な強さを感じさせる。
彼らが語る「それでも続けた理由」には、損得勘定だけでは測れない、人間としての深い葛藤と、それでもなお持ち続けようとする希望が滲み出ている。
そして、長く事業を続ける実業家たちに共通して見られる“ある種の諦念”。
それは、情熱が冷めたわけではなく、成功を追い求めないわけでもない。
むしろ、現実をあるがままに受け入れ、コントロールできないことは手放し、日々の営みを淡々と、しかし着実に積み重ねていくという、成熟した強さの現れなのではないだろうか。
最後に、読者の皆様に問いたい。
「あなたは、何を続けたいですか?」
それは事業かもしれないし、趣味や学び、あるいは人との関係性かもしれない。
対象は何であれ、「続けること」の意味と価値を、本記事が改めて考えるきっかけとなれば幸いである。
実業家たちの日常を通して見えてくるのは、単なるビジネスの教訓ではなく、我々自身の生き方にも通じる、普遍的な人間のドラマなのかもしれない。